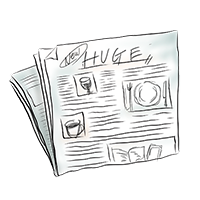レストラン屋”がつくるジン『NUMBER EIGHT GIN』の魅力。

バーテンダーが本気でつくった、フレッシュボタニカルのクラフト・ジンの秘密に迫る——。
自社製造のハウスビールに、自社焙煎のコーヒー。レストランとして、自らの手でクラフトしたものをお客様に提供する。そんなHUGEの想いが込められたプロダクトのファンは多い。HUGEのものづくりの拠点、YOKOHAMA HAMMERHEADに蒸留所を持つNUMBER EIGHT GIN (ナンバーエイトジン)も、そのひとつ。
『NUMBER EIGHT GIN』を製造する“NUMBER EIGHT DISTILLERY”の蒸留責任者であり、HUGEのコーポレートバーテンダーでもある深水稔大(以下、TOSHI)が、HUGEが初めてチャレンジをしたクラフトジンの誕生秘話を語ります。
バーテンダーが手がける、「プレゼンテーションできるジン」。
「HUGEのクラフト・ジンをつくってよ」
『NUMBER EIGHT GIN』は、代表・新川のそんな一言で動き出した——。
2019年、みなとみらいの『QUAYS pacific grill』がオープンするタイミング。1つのレストランの中に、クラフトビールのブルワリーとコーヒーのロースタリー、そしてジンの蒸留所を設置する、HUGEの中でも前例のないプロジェクトが動き出しました。蒸留責任者に抜擢されたのは、HUGEのコーポレートバーテンダーであるTOSHI。バーテンダーとしてキャリアを重ねてきたが、当時はジンづくりなどやったこともなく、蒸留家としては経験ゼロからのスタート。
「もともとクラフト・ジンには興味があり、代表の新川にジンをやりたいと話したことはありました。とはいえ、イメージしていたのはあくまでも、自分がプロデュースしたものを醸造のプロと一緒に形にしていくというスタイル。だから、新川に『ジンをつくるならトシちゃん(深水)だろう』と言われた時は、どうしようかという気持ちになりました。まずはスピリッツ製造免許を取得するところからのスタートでした(TOSHI)」
「不安が8割」という心理状態の中、1カ月の蒸留所での研修を終え、次に取り組んだのは、クラフトジンのレシピ開発。コンセプトは“レストラン屋がつくるジン”。料理に合わせやすいことはもちろん、バーテンダーとしてお客様にプレゼンテーションする際、HUGEがつくったジンという納得感がほしいと考えました。
そんな、レストランのバーテンダーらしい視点で導き出したのが、『フレッシュボタニカル』というアイデア。通常ジンにはドライのボタニカルが使用される事が多いけれど、自社に野菜を市場に買い付ける青果部を持つHUGEであれば、生の良質なボタニカルが手に入る。フレッシュな素材を使うことで、より印象的なボタニカルの香りを引き出すことを狙ったという。
「使用するボタニカルは8種。8という数字は、みなとみらいの8番埠頭に建てられた蒸留所の名前、『NUMMBER EIGHT DISTERRALLY』にちなんで決めました」 “8番埠頭で作られる、8種のボタニカルのジン”から、『NUMBER EIGHT GIN』とネーミングされることも決定。
原料のボタニカルを選定する際に意識したのは、HUGEの各業態のエッセンス。
「ジンのアイデンティティと言われる、『ジュニパー・ベリー』のほか、HUGEのモヒートに使われるミント『イエルバ・ブエナ』、蒸留所を置く神奈川県にちなんだ『神奈川みかん』、HUGEのレモンシロップやレモンサワーにも使われる『無農薬レモン』、自家製ハーブティに使用されている『レモン・バーベナ』、ハウスビールで使われる『フレッシュ・ホップ』、ピッキング工程で取り除かれたスペシャリティ・コーヒーの『珈琲豆』、そして、メキシカン業態で使用された『アボカドの種』が使われています(TOSHI)」
また、アボカドの種や珈琲豆のように廃棄を待つ食材を使う事で、フードロスの問題をサステナブルに解決しながら、“レストラン屋がつくるジン”のストーリーを深めていきました。
個性のある粕取り焼酎でジンをつくる。
クラフトマンシップをかけた挑戦。
「スタンダードを一捻りし、HUGEにしかないものをつくる」。HUGEのクリエイターたちの仕事には、そんなこだわりがあります。『NUMBER EIGHT GIN』も、そんなこだわりがたくさん詰まったクラフトジン。ジンのベーススピリッツは通常、ボタニカルの個性を引き出すための下地と理解されている。そのため、一般的にはクセのないフラットなスピリッツが使用されることが多い。
けれど、『NUMBER EIGHT GIN』は違います。ベースに使用しているのは、茨城県の酒造でつくられる「粕取り焼酎」。酒粕のアルコール分を蒸留して作られているため、鮮烈なボタニカルのフレーバーの奥にほのかにスモーキーな吟醸香が感じとれ、ユニークなアクセントになっています。
この個性を「潰さすぎず、かといって全面に個性を出しすぎず、どう表現するのか?」。ここがまさに開発の肝だったと、TOSHIは語ります。
「ジンの主役はあくまでもボタニカル。酒粕の香りが強すぎると、焼酎らしさが前面に出てしまう。かといって特徴的な吟醸香がなくなれば、面白味がありません。ボタニカルと吟醸香のバランスを調整するため、レシピは変えずに蒸留時間やボタニカルの漬け込み時間など、製造工程を何度も何度も見直しました(TOSHI)」
原料となるボタニカルの処理や分量、蒸留スピード、一つの工程を変えるだけでも、その仕上がりは大きく変わります。スタンダード味わいの中にオリジナリティが見える現在のバランスに辿り着くまでには、数々の失敗と試行錯誤がありました。
近年、ベーススピリッツに焼酎を使用したクラフト・ジンは増えてきたが、粕取り焼酎を使ったものはまだまだ見かけることが少ない。それだけ扱うのが難しい素材に向き合ったTOSHIのクラフトマンシップが、『NUMBER EIGHT GIN』には込められています。
どんな料理にもマッチする、レストラン屋のジントニック。
レストラン、バーテンダー、そしてクラフトマン。蒸留責任者のTOSHIがあらゆる視点からこだわったHUGEのクラフトジンは、2019年のデビュー以来、多くのファンに愛されてきました。ここからはそんな『NUMBER EIGHT GIN』 の魅力を最大限に引き出す、おいしい飲み方やペアリングをご紹介!
HUGEのレストランで『NUMBER EIGHT GIN』をオーダーするなら、ジントニックやジンリッキーのような定番のロングカクテルで、フレッシュボタニカルのパワーをストレートに感じるのがおすすめ。 食中酒として設計されているため、スパニッシュイタリアン、メキシカンにエスニック、どの業態の料理とも合わせやすいけれど、業態ごとにより魅力を引き出す組み合わせがあります。
たとえば、世界各国から厳選したサーモンを味わえるサーモンプレートが人気の『QUAYS pacific grill』。その中でもサーモンを『NUMBER EIGHT GIN』に漬け込み、香り付けして提供する「サーモン・ナンバーエイト」は、『NUMBER EIGHT GIN』のジントニックと楽しむことで香りや味わいが完璧にリンクする、最高のペアリング!
はたまた、『蕎麦』業態。素材を味わうシンプルな「せいろそば」には、甘さのない炭酸でシンプルに割った、ソーダ割がおすすめ。吟醸香をそのまま楽しめ、すっきりとした味わいは、素材の味わいをストレートに味わう和食によく合います。モダンメキシカンなら、ジンを使ったモヒートとタコスの組み合わせはいかがですか?『NUMBER EIGHT GIN』に使われているさっぱりとした柑橘のフレーバーが、ハラペーニョやパクチー、フレッシュライムの香りとも爽やかにマッチします。
どれを試せばいいのか悩んだら、まずはレストランで、“いつものメニュー”とジントニックを。2杯目は単品で、ご自身の好みの飲み方をバーテンダーに相談しながら、NUMBER EIGHT GINの魅力を探求してみてはいかがですか。